【運輸労連】
第63回中央委員会を開催
組合員の生活の維持向上、他産業との格差是正に向け
「大きな変化」につながる春闘へ!

中央委員会全景
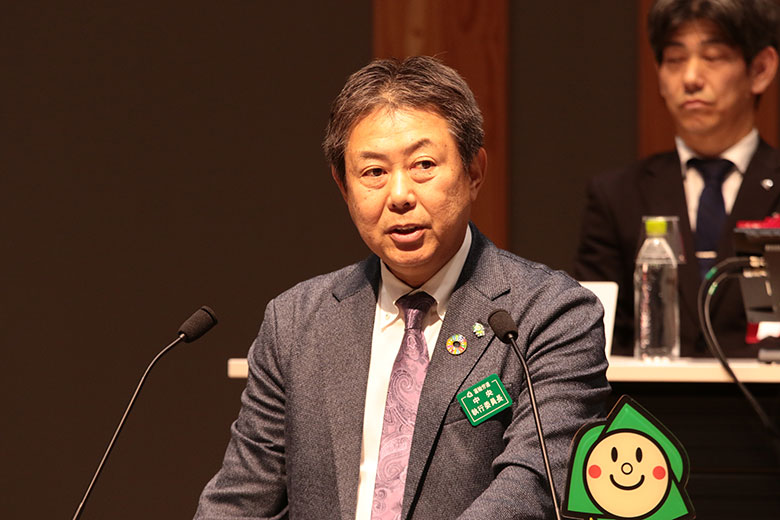
あいさつする成田中央執行委員長
運輸労連は1月21日(火)、ライトキューブ宇都宮 (栃木県宇都宮市) にて「第63回中央委員会」を開催。全国から251名(うち女性27名、女性参画率10.75%)の中央委員・傍聴者などが出席し、「2025春季生活闘争方針」を決定しました。
冒頭のあいさつで成田中央執行委員長は、今次春闘を取り巻く情勢について、「燃油費の高止まりや物価高などの影響で取り扱い物流量が減少したことに加え、適正運賃の収受が進んでいない状況にあり、厳しい企業業績にあるが、物流に対する認知度が社会全体で高まりつつある」とトラック運輸業界の置かれた状況を概括。ただし、昨年からトラックドライバーの働き方改革ともいえる「物流の2024問題」がスタートしたこともあり、「政労使、荷主企業、社会全体が私たちの業界にしっかり目を向けていただいている」として、「今こそ、働く仲間の労働環境改善、持続可能な物流を作り上げていくチャンス」と業界変革に前向きな姿勢をみせました。
2023年、2024年に続き高水準の賃上げの勢いを定着させたいという機運が社会全体で高まる中、連合方針を踏まえた運輸労連の統一要求基準については、「所定内労働時間賃金に定期昇給 (相当)分の1.5%と、他産業および業界内における格差是正分ならびにこの間の物価上昇を勘案し、賃金改善分 (含む、格差是正分・物価上昇分)としての4.5%を加えた6. 0%を乗じたものとし、賃上げ要求額は
15,500円中心」との方針が示されました。実現に向けては、「物流に対する社会全体での認知度が高まる中、2025春季生活闘争の交渉は『大きな変化』につながるよう、加盟組合の皆さんと一緒になって頑張りたい」と呼びかけました。
今年7月に控えた第27回参議院議員通常選挙における運輸労連比例代表推薦候補者の紹介では、各候補者から決意表明を受けました。また、祝電・メッセージの中から代表して、連合・芳野会長の連帯のメッセージが紹介されました。
議事では、杉山中央書記長が活動経過を報告し、第1号議案「2025春季生活闘争方針」を提案。5名の中央委員からの質疑・要望に対して中央本部役員が答弁し、絶対多数の賛成で「2025春季生活闘争方針」を可決しました。引き続き、第27回参議院議員通常選挙必勝決議(案)、スローガンが採択され、最後に成田中央執行委員長の音頭による「団結ガンバロー三唱」をもって第63回中央委員会は閉会しました。


「2025新春交歓会」に各界から多数のご来賓が出席
歴史的な転換点に立つ今こそ、新しい時代の創造・挑戦を!

運輸労連は1月7日(火)、東京・全日通霞が関ビルにおいて「2025新春交歓会」を開催しました。連合をはじめ、立憲民主党、国土交通省、全日本トラック協会、関係団体など各界の関係者約200名が一堂に会しました。
|
第63回中央委員会を開催
組合員の生活の維持向上、他産業との格差是正に向け
「大きな変化」につながる春闘へ!

中央委員会全景
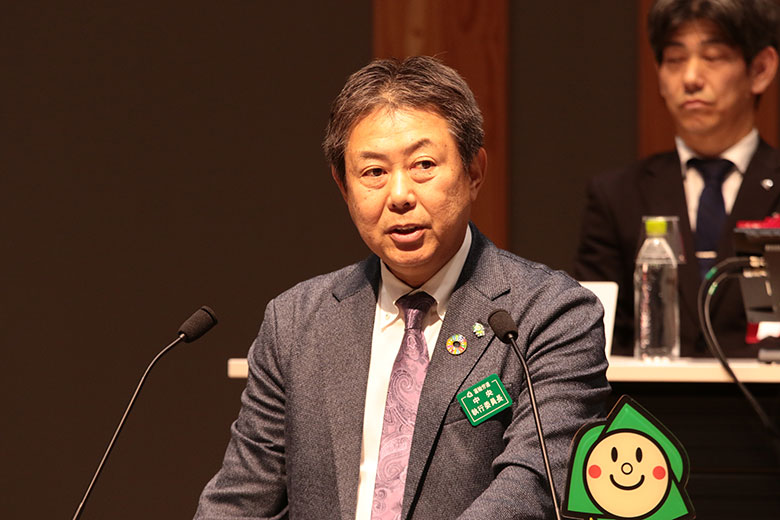
あいさつする成田中央執行委員長
運輸労連は1月21日(火)、ライトキューブ宇都宮 (栃木県宇都宮市) にて「第63回中央委員会」を開催。全国から251名(うち女性27名、女性参画率10.75%)の中央委員・傍聴者などが出席し、「2025春季生活闘争方針」を決定しました。
冒頭のあいさつで成田中央執行委員長は、今次春闘を取り巻く情勢について、「燃油費の高止まりや物価高などの影響で取り扱い物流量が減少したことに加え、適正運賃の収受が進んでいない状況にあり、厳しい企業業績にあるが、物流に対する認知度が社会全体で高まりつつある」とトラック運輸業界の置かれた状況を概括。ただし、昨年からトラックドライバーの働き方改革ともいえる「物流の2024問題」がスタートしたこともあり、「政労使、荷主企業、社会全体が私たちの業界にしっかり目を向けていただいている」として、「今こそ、働く仲間の労働環境改善、持続可能な物流を作り上げていくチャンス」と業界変革に前向きな姿勢をみせました。
2023年、2024年に続き高水準の賃上げの勢いを定着させたいという機運が社会全体で高まる中、連合方針を踏まえた運輸労連の統一要求基準については、「所定内労働時間賃金に定期昇給 (相当)分の1.5%と、他産業および業界内における格差是正分ならびにこの間の物価上昇を勘案し、賃金改善分 (含む、格差是正分・物価上昇分)としての4.5%を加えた6. 0%を乗じたものとし、賃上げ要求額は
15,500円中心」との方針が示されました。実現に向けては、「物流に対する社会全体での認知度が高まる中、2025春季生活闘争の交渉は『大きな変化』につながるよう、加盟組合の皆さんと一緒になって頑張りたい」と呼びかけました。
今年7月に控えた第27回参議院議員通常選挙における運輸労連比例代表推薦候補者の紹介では、各候補者から決意表明を受けました。また、祝電・メッセージの中から代表して、連合・芳野会長の連帯のメッセージが紹介されました。
議事では、杉山中央書記長が活動経過を報告し、第1号議案「2025春季生活闘争方針」を提案。5名の中央委員からの質疑・要望に対して中央本部役員が答弁し、絶対多数の賛成で「2025春季生活闘争方針」を可決しました。引き続き、第27回参議院議員通常選挙必勝決議(案)、スローガンが採択され、最後に成田中央執行委員長の音頭による「団結ガンバロー三唱」をもって第63回中央委員会は閉会しました。


「2025新春交歓会」に各界から多数のご来賓が出席
歴史的な転換点に立つ今こそ、新しい時代の創造・挑戦を!

運輸労連は1月7日(火)、東京・全日通霞が関ビルにおいて「2025新春交歓会」を開催しました。連合をはじめ、立憲民主党、国土交通省、全日本トラック協会、関係団体など各界の関係者約200名が一堂に会しました。
●主催者あいさつ(要旨) 中央執行委員長 成田 幸隆
|
第55回運輸セミナーを開催(2024年12月6日)
物流の「価値」を再認識して
物流改革や働き方改革を確かなものにしていこう!
|
|
第54回運輸問題研究集会(10/7~10/8)
長時間労働に頼らない賃金制度を確立し
若者や女性に選ばれる産業へ変革しよう!
|
|
運輸労連第57回定期大会 7月4日~5日 東京・浅草公会堂で開催
2024年度(中間年)運動方針を決定
労働時間の長さに依存しない賃金制度へ
|
|
|
<スローガン> |
委員長あいさつ(要旨)
 中央執行委員長 成田幸隆 |
|
運輸産業のリーダーユニオンとして |
第62回中央委員会を開催
長時間労働に依存しない賃金・労働条件の確立へ
大きな変化につながる春闘を展開しよう!

中央委員会全景

あいさつする成田中央執行委員長
運輸労連は1月24日(水)、湯本富士屋ホテル(神奈川県足柄下郡)にて「第62回中央委員会」を開催。全国から198名(うち女性20名、女性参画率10.1%)の中央委員・傍聴者などが出席し、「2024春季生活闘争方針」を決定しました。
冒頭のあいさつでは、成田中央執行委員長が登壇。先の能登半島地震と羽田空港での航空機事故に対して哀悼し、お見舞いを述べた後、今次春闘を取り巻く情勢について概観しました。その中で、いよいよ2024年4月からトラックドライバーの働き方が大きく変わること(年960時間の時間外労働上限規制の適用と改正改善基準告示の施行)について、「労働時間の長さに依存しない賃金制度へ本格的に移行する時代にきています」と強調。その原資を確保するためには、「消費者を含めた社会全体の意識改革を進めつつ、適正な取引環境を整備していくことが重要です。現地においても、積極的な発信をお願いします」と呼びかけました。
一方で、社会的に賃上げの機運が高まっており、今次春闘に対する組合員の期待が大きいことも指摘。連合方針を踏まえた運輸労連の統一要求基準として、「所定内労働時間賃金に定期昇給(相当)分の1.5%と、他産業および業界内における格差是正分ならびにこの間の物価上昇を勘案し、賃金改善分(含む、格差是正分・物価上昇分)としての4.5%を加えた6.0%を乗じたものとし、賃上げ要求額は15,000
円中心」との方針が示されました。そして、その実現に向けて、「しっかりとベクトルを合わせて取り組んでいきましょう」とあいさつを締め括りました。
続いて来賓あいさつでは、第27回参議院議員通常選挙(2025年7月)における運輸労連の推薦候補者が紹介され、各候補者から決意表明を受けました。また、多数の祝電の中から代表して、連合・芳野会長と交運労協・住野議長の連帯のメッセージが紹介されました
議事では、杉山中央書記長が活動経過を報告し、第1号議案「2024春季生活闘争方針」を提案。6名の中央委員からの質疑・要望に対して中央本部役員が答弁し、絶対多数の賛成で「2024春季生活闘争方針」を可決しました。引き続き、スローガンを採択し、成田中央執行委員長の音頭による力強い「団結ガンバロー三唱」をもって第62回中央委員会は閉会しました。


第54回運輸セミナーを開催(2023年12月7日)
人が集まる魅力ある産業へ向けて
エネルギッシュな運動を進めよう!
|
|
第53回運輸問題研究集会(10/10~10/11)
トラックの働き方に注目が集まる今こそ
私たちの現状が伝わる努力に徹しよう!
|
|
運輸労連第56回定期大会 7月5日~6日 北海道・札幌市で開催
2023~2024年度運動方針を決定
持続可能な運輸産業を構築していこう!
|
|
運輸労連議員懇メンバーの鬼木誠参議院議員が
「次世代トラック導入の現状」「軽貨物運送業の現状」について質疑

|
 2023年6月1日(木) 参議院国土交通員会 |
6月1日(木)参議院国土交通委員会において、運輸労連政策推進議員懇談会メンバーの鬼木誠参議院議員(比例)より、「次世代トラック導入の現状」「軽貨物運送業の現状」に関する質疑が行われました。
鬼木誠参議院議員:2024年2月10日、政府はGX実現に向けた基本方針を閣議決定し、今後10年間の取り組み方針が記されたが、運輸部門のGXである次世代自動車の項目で、「燃料電池自動車、電気自動車等の野心的な導入目標を策定した事業者に対して、車両導入等を重点的に支援する」旨が記されている。一方、2021年6月の経産省2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略では、「8トン超えの大型車については、貨物・旅客事業等の商用用途に適する電動車の開発、利用促進に向けた技術実証を進めつつ、2020年代に5,000台の先行導入、そして2030年までに2040年の電動車の普及目標を設定する」旨が記されているが、大型車については、まだこの技術開発が追い付いておらず遅れている状況と考えている。その中で、GX基本方針にある燃料電池自動車や電気自動車の導入目標を設定することは難しいのではないかと考えており、本当に可能かという疑問も抱いている。この次世代トラックの開発の現状について、特に燃料電池自動車や電気自動車の開発状況を国交省としてどのように把握されているかお尋ねしたい。
堀内丈太郎自動車局長:電気自動車や燃料電池自動車を始めとする次世代トラックは、航続距離や充電・充填時間などに関する電動車ごとの特性を踏まえ、小型トラックは電気トラック、大型トラックは燃料電池トラックという使用実態に合わせた技術開発がなされているものと認識している。小型の電気トラックは、国内の大手自動車メーカーなどにより既に市場投入がされ始めており、大型燃料電池トラックは、今年度より国内メーカーの車両を用いたトラック運送事業者による公道の走行実証が既に開始された。ただし、これらの車両は、従来のトラックに比べ価格差が未だ大きいことから、国土交通省として、関係省庁とも連携し、電動車の導入支援などを通じて自動車メーカーの技術開発を促進している。
鬼木誠参議院議員:次世代トラックは車体価格がエンジン車の1.5~2倍であると伺った。一方、耐用年数について、エンジン車が平均15年であるのに対し、電動トラックの蓄電池寿命が約5年しかもたないと把握している。仮にエンジン車と同様に15年乗るとすれば、最低でも2回蓄電池交換をしなければならず、費用負担が厳しいと考えている。また、故障や事故も、例えばエンジン車のエンジンが壊れた場合、壊れた部分のみ取り替えればよいが、電動トラックの場合は部品交換ではなく車ごと取り替えなければならない事態もある。
新車購入や維持に掛かるコストが共に高くなると、約9割が中小企業で約半数が経営赤字とも言われるトラック運送事業者にとって、大変な負担になる。したがって、積極的に導入をする目標は厳しいと考えている。GXを推進することは極めて重要だが、現状把握や現状に沿った目標設定または支援等が必要と考えている。次世代トラックの導入に関して、国土交通省では地域交通のグリーン化に向けた次世代自動車の普及促進事業による購入費の補助、環境省ではトラック等を集中的に支援する商用車の電動化促進事業などが設けられているが、車両価格や蓄電池交換等に掛かる費用や負担が大きいと捉えている。改めて、現在のトラック事業者における次世代トラックの導入状況はどの程度進んでいるかお聞かせいただきたい。
堀内丈太郎自動車局長:2023年3月時点で、ディーゼル車等を含めたトラック全体の保有台数ベースでは約1,400万台であり、うち次世代トラックは約10万台となっており、全体の0.7~0.8%である。ただ、2022年度の1年間におけるトラックの新車販売台数は、約71万台のうち、次世代トラックの台数は約3万1,000台と全体の約4.3%となっており、直近の1年間では5%に近い状況まで増えている。
鬼木誠参議院議員:まだ普及が進んでいないことや、大型車については実証実験が始まったとはいえ、これからの技術開発であることから、進捗を見極めていただき、具体的な支援の在り方等もより具体的にご検討いただきたい。
次に、蓄電池の交換について、蓄電池は高価であるため、電池交換の際、事業者負担の軽減をするための補助など現在検討されているかお聞かせをいただきたい。
堀内丈太郎自動車局長:蓄電池バッテリーは、通常5年以上経つと徐々に劣化するとされているが、まだ5年経っている車があまりないため、5年過ぎてどれぐらいバッテリーが劣化するかということの調査検討も進めている。
バッテリーの交換に係る負担軽減は、実証事業の結果や、市場のバッテリー交換頻度、コスト等の実態を踏まえ、関係省庁と検討し考える必要がある。これらを通じ電気トラック等の普及促進に向けて進めてまいりたい。
鬼木誠参議院議員:実証効果の把握は必要だが、効果を見極めた後に費用軽減に向けた検討となっては取り組みが遅れてしまうので、是非、実証効果や効率的な充電の検討と併せて、費用負担軽減の在り方も検討されることを重ねてお願いしたい。
それと、次世代トラックについて、性急かつ強制的に導入されることがあってはならない。トラック事業者は中小企業が多く、経営も厳しい状況の中で、次世代トラックに一斉に切り替えることを強制されると、業界全体が混乱するのではないかと心配している。1999年に東京都でディーゼル車の排ガス規制が行われたが、その対応に業界が追われ、トラックが社会悪のように言われた風潮があった。したがって、同様なことが生じることのないよう、具体的な規制と支援も含め、トラック運送事業者に過度な負担とならないことを、業界の意見を踏まえて検討すべきと考えており、大臣の見解をお願いしたい。
斉藤鉄夫国土交通大臣:2050年カーボンニュートラルに向けて、目標に向かって進めていくために、同時に支援も必要である。
まず、導入目標について、2023年4月、省エネ法に基づき、小型トラックは2030年度における保有台数の5%を電気自動車や燃料電池自動車等の非化石エネルギー自動車とする目標を設定した。この目標は、トラック運送業界からの意見も聴取しつつ策定したものであり、実現可能な水準であると思っている。
さらに、トラック運送事業者を対象とした電気自動車や燃料電池自動車の購入支援は、2023年度予算において約136億円を確保するなど、昨年度までと比較し支援を大幅に拡充している。これらの支援等により野心的な目標を達成していきたい。
鬼木誠参議院議員:目標に向けて双方で努力することがあるべき姿だと思うが、トラック運送事業者に過度な努力を求めることにならないことを重ねてお願いしたい。
次に、炭素に対する賦課金、カーボンプライシングの導入にあたっては、化石燃料の輸入業者を対象とされているが、仮にトラック運送事業者が対象となった場合、経営に与える影響が極めて大きく、企業倒産の増加につながり、物流クライシスが一層深刻化するのではないかと心配されている。
まだ、このカーボンプライシングや炭素賦課金の関係は具体的な内容が分かっていない状況であるが、運輸業者や産業への過度な負担増とならないよう慎重に検討を進めていただきたい。
斉藤鉄夫国土交通大臣:2023年5月12日に成立した「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」により、化石燃料賦課金が導入されることとなった。具体的には、化石燃料の輸入事業者などを対象とし、2028年度から輸入などを行う化石燃料に由来するCo2の量に応じて化石燃料賦課金が徴収されることとなっている。この化石燃料賦課金の水準は、今後、経済界への影響などの観点も踏まえて決定されるものと承知している。
国土交通省が所管するトラック運送事業者は、今のところ、化石燃料賦課金の徴収の直接の対象とはなっていないが、賦課金の導入に伴う間接的な影響も考えられることから、国土交通省として、トラック運送事業者にとって過度な負担増となることのないよう、注視してまいりたい。
鬼木誠参議院議員:是非よろしくお願いしたい。
次に、軽貨物運送業の現状と今後の考え方について、今年の3月、貨物軽自動車運送業者について取り上げさせていただいたが、その際、堀内自動車局長から、運行管理の実施状況など実態調査を行っているというご回答をいただいた。今月の16日に開催をされた適正化協議会で、調査結果が報告をされたが、「運行管理を行っていない」が全体の25%、改善基準告示など法令に基づく労働時間等の定めについて、「遵守をしていない」が全体の39%、改善基準告示について、遵守をしていない事業者のうち14%が基準を知らなかったという実態が明らかになっている。
心配したとおり、ずさんな状況と捉えている。前回の局長の答弁の中で、運行管理や労務管理、健康管理を実施するように改めて周知を図ったとあったが、調査結果からは、あまり実効性がないと見える。また、届出だけで事業が実施できるため、その気軽さの分、法令遵守が疎かになっている。
さらに、荷主との力関係で相当量の荷物数を引き受けざるを得ない、いわゆる荷主による違反原因行為があるという回答が54%になっている。こうした荷主への働きかけの強化についても一層強めていただきたい。改めて、実態調査の結果を踏まえ、国土交通省として結果をどのように分析されているか、今後の対応をどう考えているのかお尋ねしたい。
堀内丈太郎自動車局長:本年3月に行った調査結果を先月16日に提示し、その結果、運行管理を実施していない事業者25%、拘束期間や休息期間を遵守していない事業者も約39%いる。安全運行に係る法令を遵守していない事業者が相当程度いることが明らかとなった。
これを踏まえ、事業用軽貨物自動車の安全を確保するため、本年度は軽貨物事業者向けの運転者への指導監督マニュアルの作成や、運行管理者講習の受講を促すなどの対策を実施する方向で検討しているが、更にもう少し踏み込んだ措置を検討していく。
鬼木誠参議院議員:踏み込んだ措置について具体的な検討をお願いしたい。法改正も視野に入れるとの報道がなされているが、一定の規制強化を考えていく、そのことが踏み込んだ措置であるなら、法改正も検討されるものと思っている。
一番心配しているのは、一般の貨物自動車運送業者の方々は法律を守っている一方、法令遵守しない軽貨物事業者は気軽に事業展開をしているため、バランスが取れていないことである。この点を十分に留意していただき、仮に法改正あるいは規制を強めるのであれば、当該者や荷主の意見を聞くことも必要と思うが、一般の貨物自動車運送業者の意見も十分に聞きながら、制度化を図っていただきたい。
斉藤鉄夫国土交通大臣:これまで以上に中小のトラック事業者の方の声を聞く方向に大きく進んでいきたい。現場の声を聞いた上で法改正等を検討したい。
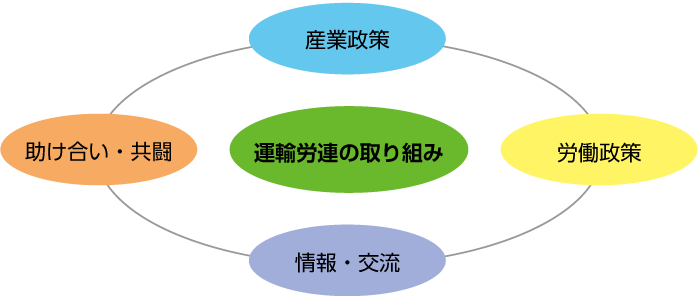
<スローガン>
構築しよう!
産業の価値に見合った賃金労働条件
進めよう!
物流諸課題に対応する産業政策
めざそう!
若者が夢と誇りをもてる魅力ある産業

 若い人たちに選んでいただける業界に「脱皮」を!
若い人たちに選んでいただける業界に「脱皮」を! 運輸労連は12月6日(金)、第55回運輸セミナーを開催(全日通霞が関ビルからWEB配信)し、全国から221名が参加(うち女性11名、女性参加率4.98%)が参加し、2025春季生活闘争に向けての情報と認識を共有しました。
運輸労連は12月6日(金)、第55回運輸セミナーを開催(全日通霞が関ビルからWEB配信)し、全国から221名が参加(うち女性11名、女性参加率4.98%)が参加し、2025春季生活闘争に向けての情報と認識を共有しました。 運輸労連は10月7日(月)~8日(火)の2日間、新潟県湯沢町「NASPAニューオータニ」にて第54回運輸問題研究集会を開催。全国から283名(うち女性7名、女性参画率2.47%)の仲間たちが参集しました。
運輸労連は10月7日(月)~8日(火)の2日間、新潟県湯沢町「NASPAニューオータニ」にて第54回運輸問題研究集会を開催。全国から283名(うち女性7名、女性参画率2.47%)の仲間たちが参集しました。 運輸労連は7月4日(木)~5日(金)の2日間、東京・浅草公会堂にて「第57回定期大会」を開催。全国から代議員・オブザーバー(WEB傍聴)など、402名(うち女性26名、女性参画率6.48%)が出席しました。
運輸労連は7月4日(木)~5日(金)の2日間、東京・浅草公会堂にて「第57回定期大会」を開催。全国から代議員・オブザーバー(WEB傍聴)など、402名(うち女性26名、女性参画率6.48%)が出席しました。 労済>・濱田常務理事ほか、来賓のご臨席を賜りました。
労済>・濱田常務理事ほか、来賓のご臨席を賜りました。 況にも触れ、政権の裏金問題について「国民は納得できていない。こんな政治は終わらせなければならない」と強調し、政治のリセットへ向けた団結を訴えました。その他、ジェンダー平等や多様性推進の重要性にも言及し、誰もが安心して働ける社会の実現に向けた連帯のメッセージを締め括りました。
況にも触れ、政権の裏金問題について「国民は納得できていない。こんな政治は終わらせなければならない」と強調し、政治のリセットへ向けた団結を訴えました。その他、ジェンダー平等や多様性推進の重要性にも言及し、誰もが安心して働ける社会の実現に向けた連帯のメッセージを締め括りました。 運輸労連は12月7日(木)、第54回運輸セミナーを開催(全日通霞が関ビルからWEB配信)。全国から253名が参加(うち女性9名、女性参加率3.6%)し、2024春季生活闘争に向けての情報と認識を共有しました。
運輸労連は12月7日(木)、第54回運輸セミナーを開催(全日通霞が関ビルからWEB配信)。全国から253名が参加(うち女性9名、女性参加率3.6%)し、2024春季生活闘争に向けての情報と認識を共有しました。 運輸労連は10月10日(火)~11日(水)の2日間、新潟県湯沢町「NASPAニューオータニ」にて第53回運輸問題研究集会を開催。全国から297名(うち女性8名、女性参加率2.7%)の仲間たちが参加しました。
運輸労連は10月10日(火)~11日(水)の2日間、新潟県湯沢町「NASPAニューオータニ」にて第53回運輸問題研究集会を開催。全国から297名(うち女性8名、女性参加率2.7%)の仲間たちが参加しました。